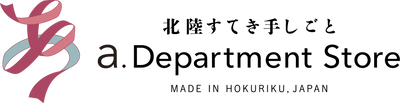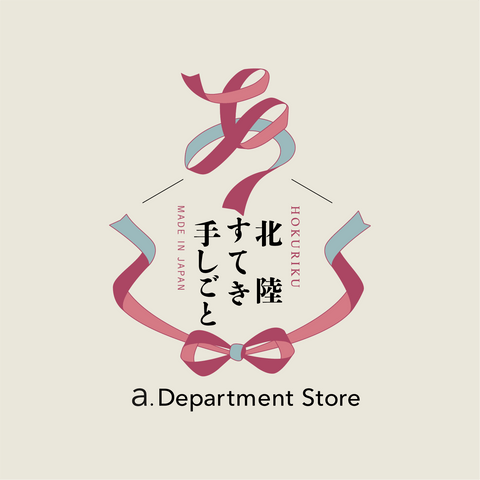みなさん、こんにちは。
今回の読み物は日本酒についてです。
奥深い日本酒については、一言では語れませんし、私自身もまだまだ勉強途中ですが、最初の基本のきの部分を書いていきたいと思います。
まず、日本酒の原料はなんでしょうか。米と水と米麹です。
日本酒はその原料を使い、世界でも類を見ない、“並行複発酵”という高度な醸造方法で作られています。この原料でアルコール発酵を行うのですが、そもそもアルコール発酵には糖分が必要です。米には糖分が含まれていないため、まずは、麹を使い、米のデンプンをぶどう糖に変え、酵母の力でアルコール発酵を行います。この2つの化学反応を同時に同じタンクで行うことを並行複発酵と言うそうです。ちなみにビールは糖化を行ってからアルコール化します。また、ワインは原料に糖分が含まれるため、酵母を加えることでアルコール発酵が進みます。
この類を見ない醸造方法は、蔵人(くらびと)の経験と技が生きています。蔵人とは、お酒造りに携わる職人さんたちのことです。また、酒造りの最高責任者を「杜氏(とうじ)」と言います。当時は酒造りの全工程を管理・指揮し、その指示のもと実務を蔵人が行います。蔵人は、酒米の蒸し、麹造り、酒母造り、搾り、道具の整備など、酒造りの各工程を分担して、担当します。ですので、一人一人の経験や技がお酒造りには非常に影響し、出来上がりが異なってくるのです。




そもそもの原料であるお米、水の豊さも大切です。美味しい日本酒を作るために、自ら自社でお米作りから始める酒蔵もあるほどです。日本酒作りが盛んな福井県では、最高級酒米の「山田錦」と「越の雫」を交配させて大吟醸用の酒米「さかほまれ」を開発しました。減農薬・減化学肥料で特別栽培され、雑味の少ない洗練された甘みと香りのある、上質な日本酒を生み出す酒米として注目されています。


もう一つ、お酒の美味しい季節。旬はいつ?という疑問にお答えしたいと思います。エーデパでも最近発売した秋上がりの日本酒がありますし、夏には冷酒として飲まれる日本酒もありますね。
一般的な日本酒の旬というと、秋に酒米を収穫し、冬に醸造期間、春夏に熟成をして秋に完成という味わいが深まる「秋頃」になります。しかし、最近では1年を通じて、四季ごとの旬を楽しむことができるようになってきました。
冬に味わえる新酒は、その年の秋に収穫された新米を使って造られ、搾りたてでフレッシュな味わいが特徴です。微炭酸を含むこともあります。
春に日本酒を選ぶ際は、桜や花をモチーフにした華やかなラベルがおすすめです。春酒は、3月頃から出回り始め、新酒のフレッシュな味わいに、薄濁りや微発泡、フルーティーで飲みやすいタイプが多く、春の気分にぴったりです。生原酒も多く見られます。
夏酒がスタンダードになってきたのは、ここ15年ほどのことだそうです。夏の暑い時期にはビールやレモンサワーなどサッパリとした酒が好まれることもあり、工夫を凝らして、「夏にぴったりの酒」をつくりリリースしているのが「夏酒」。生酒、原酒、にごり酒、低アルコール酒などが多くみられます。さっぱりすっきりとした味わいを楽しめます。
このように、四季それぞれに違いを楽しめる日本酒造りが酒蔵ごとに行われています。水やお米にこだわり、一つ一つの過程に手をかけ造られる日本酒は、日本の宝と言えるでしょう。
私自身もお酒は得意な方ではありません。アルコールを摂取すると顔が即座に赤くなります。しかし、エーデパの仕事に携わるようになり、酒蔵を見学させてもらったりお話を聞いたりしたことで、日本酒のファンになりました。量を飲めないので、味わう程度ですが、手と心をかけて育まれた様子を想像しながら、自分なりに楽しんでいけたらと思っています。
**
五十嵐郁子(五十嵐羅紗店1代目店主孫娘)
1975年生。東京在住。エーデパディレクター。福井県越前市生まれ。日本女子大学卒。大学生の2人の娘の母。東京福井県人会理事。福井市応援隊サポーター。