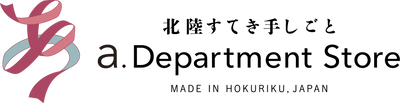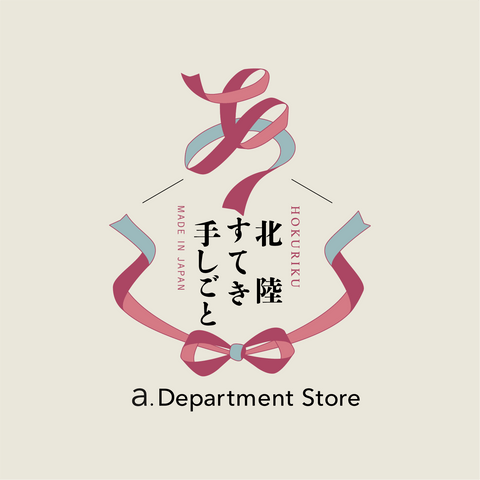みなさん、こんばんは。私は「うるしの駒や」の薮下先生の金継ぎ教室に今年の春から通い始めました。金継ぎは、割れた器を直す技術として古くから受け継がれてきたものですが、その金継ぎにもいくつもの種類のうるしを使用します。華やかな金がどうしても目に入ってしまうので、うるしの存在は実は「え?ここにもうるしが」と驚いていました。

うるしは、固まると非常に丈夫で耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。非常に優れた素材のため、昔から、塗料、接着剤、装飾に使われてきました。そのような塗料になるまでのお話を少しだけお話ししたいと思います。
うるしは木です。樹齢10年〜15年以上の木から漆を採取します。うるしの木に刃物で傷をつけて、にじみ出てくる樹液をヘラで集めます。これを漆搔きと呼び、この作業を行う人たちを漆搔き職人といいます。6月から9月にかけて行われる漆搔きですが、1本の木から採取できる漆はほんのわずかです。

また、漆搔きの技術はユネスコ無形文化遺産に指定されているほど、貴重な技術となっています。
現在では、1年でより多くの漆を採取してから、伐採する殺し搔きが主流となっています。殺し。。となると物騒ですが、ぐるりと一周傷つけることで漆が出るのを防ぎ、伐採すると、周りから小さな芽が出てきます。これを育てていくのです。伐採されたうるしの木の周りに小さな芽が出るのを想像して、命が大切に受け継がれていくことにホッとしてほっこりしました。
採取したばかりの漆は「荒味(あらみ)」と呼ばれ、木屑などの不純物を取り除き、水分を飛ばすなどの精製をほどこしたものが「生漆(きうるし)」です。生漆は乳白色の油状液で、このまま「摺り漆(すりうるし)」として使ったり、さらに精製して「透漆(すきうるし)」などの塗料に加工したりします
この生漆の水分を抜けば飴色の半透明な油状態になります。また、この水分を抜く作業を「クロメル」といい、クロメル(水分を抜くこと)には、太陽熱か炭火で漆の水分を蒸発させながらゆっくりと攪拌していくと次第に光沢が出てきます。この攪拌作業を「ナヤシ」(練ること)といいます。この水分を抜いて「ナヤシ」をし、用途に応じて、顔料や油を混ぜたりして塗料を作っていくのです。
塗料としての漆が出来上がった後に、幾度も塗り乾かしながら、塗り重ね、磨き、装飾を施したりと、さまざまな技術を集積して漆器が完成するのです。完成したのち、みなさんの手に届いた後も、うるしの品々は時間が経つにつれて色が少しずつ変化していきます。決して色褪せるのではなく、色濃く深くなっていきます。



このように漆器はうるしの木を育てるところから始まり、たくさんの人の手を介して、長い時間をかけて出来上がっていきます。もし、お家に漆器があったなら、じっくり見てみてください。もっと愛おしく感じ、漆が経年変化する様も楽しく感じることができると思います。
**
五十嵐郁子(五十嵐羅紗店1代目店主孫娘)
1975年生。東京在住。エーデパディレクター。福井県越前市生まれ。日本女子大学卒。大学生の2人の娘の母。東京福井県人会理事。福井市応援隊サポーター。
**