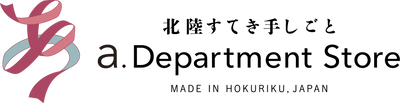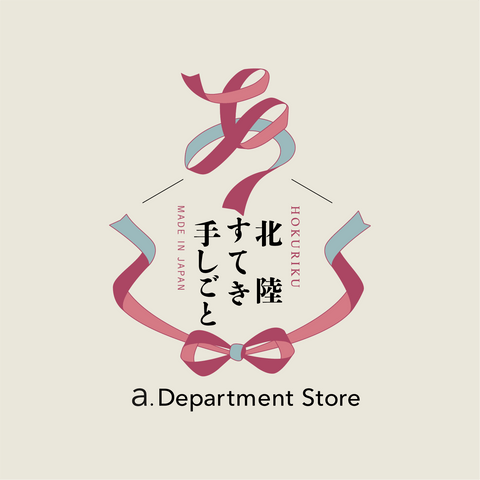みなさん、こんにちは。婚礼や入学式、卒業式などハレの日は、もちろん、葬儀などのセレモニーには欠かすことのできない真珠。今回は、その真珠ができるまでのお話を僭越ながら、私が書かせていただきます。
日本で販売されている真珠のほとんどは養殖です。天然の真珠の貝は、数千分の一くらいの割合でしか見つからないので、あこや貝の赤ちゃんを育てるところから、真珠が出来上がるまで、全て職人さんの手仕事によって作られていくのです。
あこや貝の赤ちゃんも、人工採苗で貝殻の内面の色が美しい殻幅(二枚貝で、両殻を合わせたときの殻の厚みで最も大きい幅。巻貝では殻を側面から見たとき最も大きい幅。)の厚い優れた母貝を選んで、人工交配を行なって作られていきます。約1ミリになったあこや貝の赤ちゃんを育てていきます。
孵化したあこや貝の赤ちゃんは、水槽の中で浮遊生活を送り15~25日間ほどで定着生活にはいります。定着生活にはいる頃、「沖出しカゴ」に入れて9~10月頃に殻長が約10mmになるまで海で育成します。
沖出ししたあこや貝の成長はとても著しく、真珠になる核を容易く挿入し、良質の珠ができるように、貝の生理活動の調整を行います。窮屈な状態のカゴで成長を抑制したり、刺激を与えて、産卵させて卵を抜いたりします。

そして、仕立てが終わったあこや貝に「核入れ」「珠入れ」を行うのですが、無理やり貝殻を開けると貝の閉じる力が強いために、せっかく育てた貝が割れたり、貝柱が切れたりするので、その前に一手間二手間かけます。貝が自分で大きく口を開けてもらうために、箱にぎっしり詰めて立てて長時間貝を苦しめた状態で海中に吊るしておく「貝立て」を行います。貝立ての後、海水で満たした水槽内に開放すると、一斉に大きく口を開けるのです。その口にくさび形の栓をさし「栓さし」をして、開けたままにしておきます。


やっと「核入れ」「珠入れ」を行うことができます。ここまで約1〜2年の月日が流れています。
あこや貝の生殖巣にピースと真珠核を挿入し、真珠袋を形成させるいわゆる手術をします。その後は、術後の回復を早めるために潮の流れの少ない漁場で2〜3週間ほど静かに養成します。まるで人間の術後と同じようですね。笑
そのように大切に大切に育てていくのですが、美しい真珠が出来上がるまでには、この後、1〜2年かかります。

色、照り、艶の良い良質な真珠質を分泌させて多くの真珠層をまかせたり、水温、塩分を測定しながら貝に付着するフジツボなどの除去など、さまざまな管理作業を必要とします。あこや貝のストレスも考えながらの慎重な管理だそうです。
核入れを行なってから1〜2年して、やっと浜揚げ。貝を粉砕し、肉片を洗い流して、底部に隠れた真珠を取り出します。その真珠を塩で磨き上げ、水洗いした後に、商品価値のある浜揚げ珠、商品価値のない有機質真珠、核のままのシラ珠、ケシ珠などに分類されます。ここまで毎日毎日我が子を育てるように育てた真珠ですが、全てが美しい真珠に育つとは限らないのです。
見慣れない私には、どれも美しく見える真珠ですが、美しい真珠には基準があるそうです。
「てり(照り)」:真珠層が整然と並ぶことで生まれる、深みのある光沢。
「巻き」:核の周りの真珠層の厚さで、厚いほど高品質で耐久性も高い。
「形」:真円に近いほど良いとされますが、美しいドロップ形なども含まれます。
「キズ」:表面に目立った傷がないこと。
「色」:色ムラが少なく均一なもの
このように「てり」「巻き」「形」「キズ」「色」の五つの基準をクリアしたものが高価格の真珠となります。また、色もゴールド、クリーム、グレー、イエロー、ブラック、ピンク、ホワイト、ブルー、グリーン、シルバーと様々な色がありますね。真珠層に付着したタンパク質や炭酸カルシウム、有機物などがこの色に関係してきます。


真珠には「純粋」「健康」「富」「円満」「愛情」などの意味合いがあるようです。真珠の成長を書き記したように、貝の中で異物から身を守りながら、美しい輝きを纏っていく様はまさに縁起の良い、優しい願いを込めた美しさの象徴と言えるでしょう。
**
五十嵐郁子(五十嵐羅紗店1代目店主孫娘)
1975年生。東京在住。エーデパディレクター。福井県越前市生まれ。日本女子大学卒。大学生の2人の娘の母。東京福井県人会理事。福井市応援隊サポーター。
**